テレアポ代行は「テレアポは難しい」「テレアポに割ける人材がいない」と悩む企業におすすめのサービス。
しかし「どこに外注すべきかわからない」と悩んでしまう企業も多いです。
結論から言いますと、外注先に求める内容に応じて、おすすめの外注先は変わってきます。
- 小規模案件で気軽に試すなら「クラウドソーシングサービス」
- 架電リスト・トークスクリプトの作成も依頼するなら「テレアポ代行会社」
- テレアポ以外も外注依頼したいなら「営業代行会社」
クラウドソーシングサービスなら「コール100件」など小ロットから依頼でき、代行会社に依頼するよりも安価です。
また代行会社に依頼する場合は「架電リスト」や「トークスクリプト(テレアポの台本)」の作成を任せることも可能だからですね。
この記事では「テレアポにおすすめの外注先」「依頼方法」「費用相場」「注意点」について解説しています。
記事を読み終わるころには、最適な外注先の見つけ方がわかることでしょう。
テレアポにおすすめの外注先3選|それぞれの概要と依頼方法
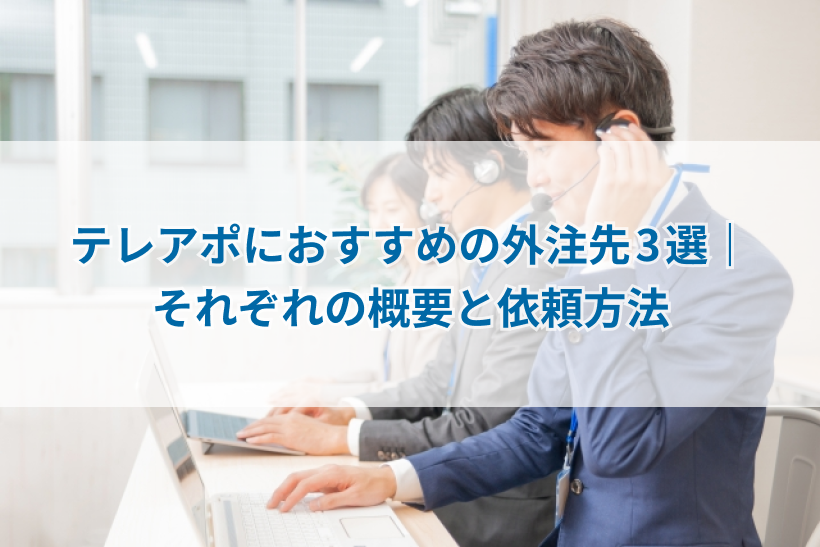
テレアポにおすすめの外注先としては、以下の3つがあります。
- クラウドソーシングサービス
- 営業代行会社
- テレアポ代行会社
この章ではテレアポでおすすめの外注先について、概要や依頼方法を紹介します。
コール件数が少ない→クラウドソーシングサービスがおすすめ
テレアポのコール件数が少ないなら、クラウドソーシングサービスがおすすめ。
個人アポインターへの依頼となるので、「コール件数が100件程度」などの小規模な案件でも外注可能だからです。
以下のようなメリットもあります。
- 登録は無料なので、初期費用がかからない
- コール単価30~50円ほどで依頼できて安価
「予算やコール件数に上限がある」とか「テレアポ代行会社に外注する前に、アポ獲得率を調査したい」といったケースで活用できるでしょう。
ただ以下のようなデメリットもあるので注意しましょう。
- 在宅アポインターの質に差があり、期待する成果に至らないケースがある
- 架電リストやトークスクリプト(台本)の作成依頼はできないことが多い
クラウドソーシングでの依頼方法は「案件を公開して応募を待つ」
クラウドソーシングサービスでは「プロジェクト方式」「タスク方式」「コンペ方式」「直接依頼」などの依頼方式が用意されています。
テレアポを外注したい場合には、案件を公開して応募を待つ「プロジェクト方式」が一般的です。
プロジェクト方式での依頼は、以下の流れで進みます。
- 【依頼者側】テレアポの依頼内容(単価・件数・納期など)を公開
- 【アポインター側】案件に応募
- 【依頼者側】応募者の中から外注先を決定
例えばクラウドソーシングの『Craudia(クラウディア)』には登録者が月間1,000人以上(※1)いるので、経験豊富なアポインターが見つかる可能性も。
サイト上では他社の依頼内容を見られるので、単価や「アポインターに伝わりやすい依頼の書き方」の参考にできますよ。
また登録しているワーカーを得意分野で絞り込み、テレアポ経験がある人に直接相談も可能です。
ご興味がある方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
テレアポ以外の営業活動も外注したい→営業代行会社がおすすめ
テレアポ以外の営業活動も外注したいなら、営業代行会社への外注依頼がおすすめです。
営業代行会社なら、「営業戦略のコンサルティング」や「商談への同行」など、テレアポ以外の営業活動にも幅広く対応できるからですね。
もちろんテレアポについても、架電リストやトークスクリプトの作成などを含めて、まるごと依頼できます。
営業代行会社が対応できるサービスには、以下のようなものがあります。
- メール営業
- 飛び込み営業
- 既存顧客へのアップセル(高価格帯商品への買い替え)営業
- インバウンド営業(WEB集客など)
- DM、ポスティング
- 営業スタッフへの研修
- 市場調査、営業戦略の立案、コンサルティング
営業活動をまるごとサポートしてほしいなら、営業代行が向いています。
例えば以下のような企業におすすめです。
- 商品開発には強いが、営業活動が苦手
- 商談を担当できる営業職が足りない
ただデメリットもあるので、以下の点を頭に入れておきましょう。
- 依頼内容によっては費用が高くなる
- 商材・希望内容によっては代行を断られる可能性あり
営業代行会社への外注依頼方法は「希望内容を伝えて見積もり依頼」
外注先候補となる営業代行会社が見つかったら、希望内容を伝えて見積もりをとるところから始めましょう。
扱う商材や代行を依頼したい営業活動によって、外注費用が異なるからですね。
発注までの流れは以下のとおりです。
- 【依頼者側】ヒアリングで要望を伝え、見積り依頼
- 【営業代行会社側】見積もり作成
- 【依頼者側】見積もりに納得したら発注
外注依頼にあたっては、いくつかの営業代行会社から見積もりをとるのがおすすめ。
予算のほか「担当者が丁寧にヒアリングしてくれるか」などを比較して選びましょう。
ただ営業代行会社は数が多いため、見積もりをとる会社を見定めるのにも時間がかかります。
その場合は「コンペル」など、外注先探しについて相談できるサービスを利用してみるのもおすすめです。
テレアポのみ依頼したい→テレアポ代行会社がおすすめ
テレアポのみ依頼したいなら、テレアポ代行会社への外注をおすすめします。
テレアポ代行のみに特化しているため、営業代行会社よりも費用を抑えやすいからですね。
また以下のようなメリットもあります。
- 大量のコールに対応できる
- コール数が多い場合には割引を受けられる可能性
- 架電リスト・トークスクリプト作成も可能
「コール件数が多いため個人には依頼できないが、費用はできるだけ抑えたい」「商談は商品を熟知した自社スタッフで行いたい」という会社におすすめです。
ただ以下のようなデメリットがあることには注意しましょう。
- クラウドソーシングサービスよりは費用が高め
- 代行会社によってコールスタッフの質にバラつきがある
テレアポ代行会社への外注依頼方法は「希望内容を伝えて見積もり依頼」
テレアポ代行会社への依頼方法は、「希望を伝えて見積もりをとる」ことからはじめましょう。
扱う商材やコール件数などによって、外注費用が異なるからですね。
発注までの流れを紹介します。
- 【依頼者側】ヒアリングで要望を伝え、見積り依頼
- 【テレアポ代行会社側】見積もり作成
- 【依頼者側】見積もりに納得したら発注
いくつかのテレアポ代行会社から見積もりをとり、比較してから選びましょう。
予算の面はもちろん、「専任の担当者がついてくれるか」「担当者が丁寧にヒアリングしてくれるか」といった部分があげられます。
ただテレアポ代行会社は多数存在するので、「どこに見積り依頼しようか迷う」といったお悩みも。
その場合は「アイミツ」など、希望に合う複数の業者から一括で見積もりがとれるサービスを試してみるのもおすすめです。
テレアポを外注依頼する時の費用相場は料金形態によって変わる
テレアポの料金形態には、主に以下の3つがあります。
- コール課金型
- 月額固定型
- 成果報酬型
この章では3つの料金形態の「費用相場」と「料金発生の仕組み」について解説します。
【コール課金型】外注費用目安は30~150円/コール
コール課金型は1コールごとに料金が発生する、シンプルな料金形態です。
コール課金型では、1コール=30円〜150円程度が相場となっています。
料金に幅があるのは、外注先によって単価が異なるからですね。
クラウドソーシングサービスだと「30~50円/コール」、代行会社だと「80~150円/コール」が相場です。
また外注先によっては「初期費用」や「アポ獲得時の成功報酬」がかかることもあります。
なおコール課金型が向いているのは、アポを獲得しやすい商材です。
アポ獲得率が高い場合、コール課金型を採用することで1件のアポ獲得にかかるコストを抑えやすくなるからですね。
一方でアポ獲得率が低い商材だと、アポをとれないまま費用負担が膨らみやすいので注意しましょう。
【成功報酬型】外注費用目安は10,000〜50,000円/1アポ
成果報酬型はアポ獲得件数に応じて課金される料金形態です。
成功報酬型の費用相場は「10,000〜50,000円/1アポ」となっています。
単価に幅があるのは、外注先や「商材ごとのアポ獲得難易度」によって料金が大きく異なるからです。
また外注先によっては「スタッフの研修費用」などの初期費用がかかることもあります。
成果報酬型が向いているのは、アポ獲得率が低めの商材。
コール課金型のように「アポ獲得できないまま費用がかさんでいく」というリスクがないからですね。
ただ成約する見込みが低い顧客のアポ(低品質なアポ)に対しても、報酬を支払う必要が出てくる点は注意しましょう。
【固定報酬型】外注費用目安は月二十万〜数十万円/月
固定報酬型とは、「週いくら」「月いくら」などの固定料金を支払う料金形態。
固定報酬型の費用相場は月二十万〜数十万円です。
料金に幅があるのは、「外注先」「扱う商材の難易度」「コール数」などにより費用が変わるからですね。
初期費用がかかる代行会社もあるので、契約前にしっかりチェックしましょう。
固定報酬型のメリットには、以下のようなものがあります。
- アポ獲得が多くても、料金が一定額を超えない
- データ分析などのサービスがついている
一方で、以下のようなデメリットもあります。
- アポが取れなくても料金を支払う必要がある
- 固定費が発生するので依頼のハードルが高い
- 基本的には長期の契約になる
長期の固定費が発生してしまうため、導入を躊躇してしまう企業も多いです。
テレアポを外注依頼する際に役に立つ「5つのコツ」
テレアポを外注する前にチェックしておきたい「5つのコツ」を紹介します。
チェックを十分にせず知名度や安さだけで選ぶと、失敗することもありますよ。
外注先の得意分野が自社商材とマッチしているか
外注先の得意分野が、営業をかけたい商材とマッチしているか確認しましょう。
テレアポ代行会社により、「IT業界での実績が豊富」「不動産賃貸に強い」など、得意分野が違うからです。
また「BtoB(企業間の取引)特化型」か、「BtoC(企業対個人の取引)の実績が豊富」かといった違いもあります。
商材と外注先の得意分野がマッチしていれば、「アポ獲得率」や「獲得したアポからの成約率」が高くなりやすいです。
テレアポ会社・営業代行会社の公式サイトで実績や取引先が確認できるので、「同業界や類似商材での実績があるか」をチェックしましょう。
任せたい業務に対応できる外注先を選んでいるか
テレアポでは実際の架電(電話をかけること)だけではなく、以下のような業務も発生します。
- 架電リストの作成
- トークスクリプトの作成
- アポ獲得率の把握
- アポが取れなかった架電先の反応分析
外注したい業務をピックアップし、任せたい内容全てに対応できる外注先を選びましょう。
外注先によっては、「トークスクリプトの作成には対応しない」「架電リストは提供してくだい」と、希望するところもあるからです。
とくに「架電リスト」と「トークスクリプト」の質は、アポ獲得件数に大きく影響します。
そのため、リスト作成とトークスクリプト作成も任せられる外注先を選ぶのがおすすめと言えるでしょう。
アポの質にこだわっている外注先を選んでいるか
テレアポ外注時には、アポの「質」にこだわっている会社・アポインターに依頼するのがおすすめです。
獲得したアポの質が低いと、商談しても受注につながらず、テレアポの外注費がかさむばかりで自社の利益にはならないからです。
高品質なアポ獲得に自信がある会社のサイトには、「獲得したアポからの成約率」が掲載されていますよ。
また「リノアーク」のように、「担当者クラスではなく、決済者クラスとのアポ比率が高い(=成約につながりやすい)」ことをセールスポイントにしている代行会社もあります。
通話音声データやコール履歴が提出可能か
「コールスタッフの通話音声データ」や「コール履歴(ログ)」が提出可能かも確認しましょう。
音声データやコールログで、以下の内容をチェックするためですね。
- 外注先が本当に電話をかけ、適切な営業をしているか
- トークスクリプトの改善点はないか
- 顧客の反応はどうか
悪質な外注先だと「実際には架電していない」「電話はしているが、決められたトークスクリプトを守っていない」こともあります。
悪質業者にひっかからないためにも、音声データやログを提供してくれる外注先を選んでいきましょう。
見直し・改善に対応可能か
外注先がテレアポ業務の見直し・改善に臨機応変に対応可能かも確認しましょう。
多くの営業担当者・コールスタッフが感じているように、テレアポは断られることが多く、1回で成功するのは難しい業務です。
そのため、質の高いアポを多く獲得するためには、適宜トークスクリプトや電話をかける時間帯などの見直しをする必要があります。
見直しや改善に対応してくれる外注先であれば、アポ獲得率の向上が見込めるでしょう。
担当者がついてくれる代行会社なら、見直し・改善についての相談がしやすくなります。
テレアポを外注依頼するメリットは3つ
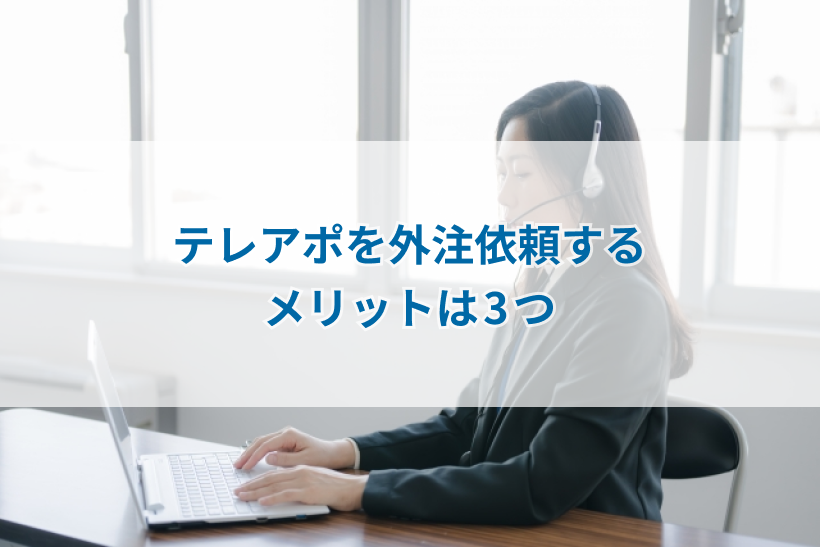
テレアポを外注依頼するメリットについて解説します。
メリット1:効率のいい営業活動が可能になる
テレアポを外注依頼すれば、営業活動の効率をあげられます。
自社スタッフがテレアポを行う必要がなくなり、アポ獲得後の商談に専念できるからですね。
テレアポにかかっていた時間を資料準備や商談に割けるるため、営業担当者はより丁寧な営業活動ができるでしょう。
また以下のようなメリットも考えられます。
- 営業担当者がテレアポによるストレスを感じなくなる
- 既存顧客へのフォローにも、今までどおり取り組める
メリット2:人件費・設備費が抑えられる
テレアポを外注依頼することで、人件費と設備費を抑えられます。
テレアポ業務を自社で行う場合に必要となる「スタッフの採用と教育」や「電話・PCなどの設備」が不要になるからですね。
テレアポに力を入れている企業ほど人件費・研修費や設備費は大きくなりますが、アウトソーシングすることでかかる支出を大きく減らせることでしょう。
また将来的にテレアポ業務が必要なくなった場合、外注への業務委託であれば契約を解除するだけで済みます。
一方自社スタッフでテレアポを行っている場合には、テレアポ業務がなくなっても簡単にはスタッフを解雇できないため、人件費がかかり続けます。
メリット3:アポ獲得率がアップする可能性
テレアポを外注依頼すれば、アポ獲得率のアップも実現できるはずです。
外注先のテレアポスキルやノウハウを活用できるからですね。
テレアポは「ただ電話をかけてトークスクリプト通り話せばいい」というわけではなく、「豊富な知識」や「高いスキル」が必要な業務。
そのため自社スタッフでテレアポを行う場合には、「スタッフがスキルを身につけるまでの準備期間」が必要です。
つまり、思うようにアポを獲得できない期間が長くなる可能性も考えられますね。
一方でテレアポを外注依頼すれば、「テレアポ業務に専念してスキルを磨いているプロ」が業務にあたるため、導入後すぐに高いアポ獲得率が期待できます。
テレアポを外注依頼するデメリットも3つ
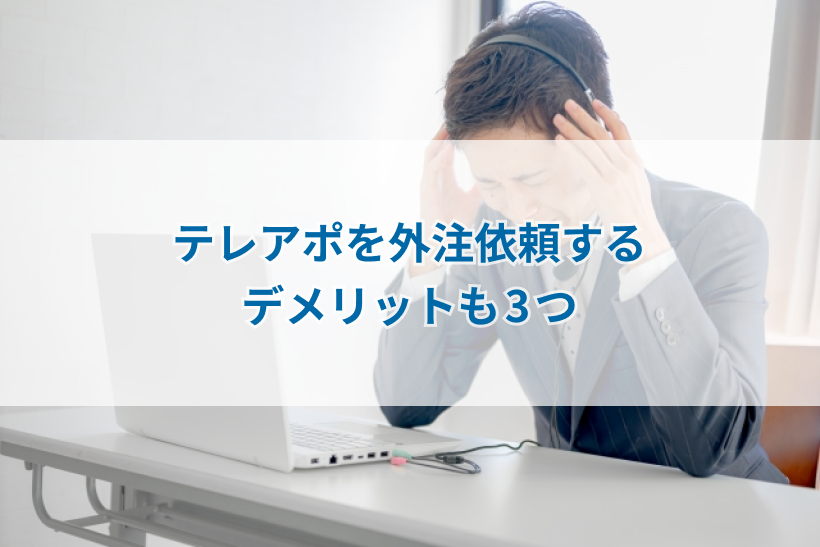
テレアポを外注依頼する場合のデメリットについても紹介します。
デメリット1:外注先により成果に差がある
デメリットのひとつめは、外注先により「アポ獲得件数」や「獲得したアポの質」に差があることです。
理由としては以下のようなことが考えられます。
- 商材と外注先の得意分野がマッチしていない
- 担当するコールスタッフが経験不足
さらに質の低い代行業者やアポインターに外注依頼をした場合には、自社の評価が下がってしまう危険性もあります。
例えば、「電話営業が強引でしつこい」「スタッフの言葉遣い・礼儀がなっていない」などが挙げられます。
デメリット2:コール課金型は成果が出なくてもコストがかかる
コール課金型の場合、テレアポの成果がでなくても費用がかかります。
架電件数に課金されるため、アポの獲得有無に関わらず費用が発生する仕組みだからですね。
アポがまったく獲得できなかったのに費用が発生するケースも少なくありません。
そのため以下のようなケースでは、成果報酬型での契約を検討するのがおすすめです。
- アポ獲得件数に応じて支払いたい
- アポ獲得のハードルが高い商材のテレアポを依頼したい
ただ「ビズコール」のように、コール課金型ながら「アポ獲得保証制度」を設けている代行会社もあります。
コール課金型を検討するなら「アポ獲得保証」や「アポが取れなかった場合の返金保証」を設けている代行会社を選んでいきましょう。
デメリット3:情報漏えいのリスクがある
テレアポを外注することで、情報漏えいが起こるリスクもあります。
外注先に対して、テレアポ業務の中で必要となってくる「会社や商品に関する社外秘の情報」や「顧客情報」を渡すケースもあるためです。
そのためテレアポを外注依頼する際は、以下のような対策をとりましょう。
- 秘密保持契約書(NDA)を交わす
- 個人情報保護研修などを行っている外注先と契約
- プライバシーマークを取得している外注先と契約
まとめ
テレアポのおすすめ外注先と、外注依頼するときのコツについてお伝えしました。
小規模案件でテレアポ外注を考えているなら、「Craudia(クラウディア)」などのクラウドソーシングサービスがおすすめ。
クラウドソーシングサービスを通じて個人アポインターに依頼すれば、少ないコール数から外注できるうえ、代行会社に依頼するよりも安価だからです。
ただ「アポインターによりスキル・実績の差が大きい」というデメリットはあります。
「コール件数が多い」「多少費用がかかってもいいからアポ数を獲得したい」「アポの品質保証や返金保証がほしい」という場合は、代行会社がおすすめです。
テレアポだけを外注依頼するならテレアポ代行会社、テレアポ以外の営業サポートも必要なら営業代行会社を選びましょう。
外注依頼するときには「実績」「獲得できるアポの質」「料金形態」などに注意してくださいね。
この記事がテレアポの外注依頼に悩んでいる方の参考になれば幸いです。
最後に当記事の監修者、株式会社AlbaLinkの河田憲二氏からコメントいただいているので紹介します。
テレアポの外注する際の参考にしてみてください。

弊社でもテレアポ外注を一部取り入れておりますが、外注先を選定する時は目的に立ち返ることが大切です。
単純に営業が弱いからアウトソースしたいという理由では失敗に終わります。
アポイントを取るだけが目的なのか、リスト獲得が目的なのか、ヒヤリング調査なのか、営業の一部と考えてもその機能を細分化して、スクリプトもより明確にすることができればプロジェクトは成功しやすくなるでしょう。
■プロフィール
株式会社AlbaLink代表取締役
河田憲二氏
独学にて不動産賃貸業・不動産売買業の知識を学び、大家業・不動産管理業・不動産売買業など不動産関連の会社を数社経営。
これまで手がけた物件は、シェアハウス・旅館・築古アパート・コワーキングスペース・貸会議室・新築・賃貸併用住宅など多岐に渡る。
運営する訳あり物件買取PROでは、年間3,000件以上の不動産売買に関わる相談を受けている。個人としても自宅用として中古物件・新築物件を取得している不動産の専門家。






